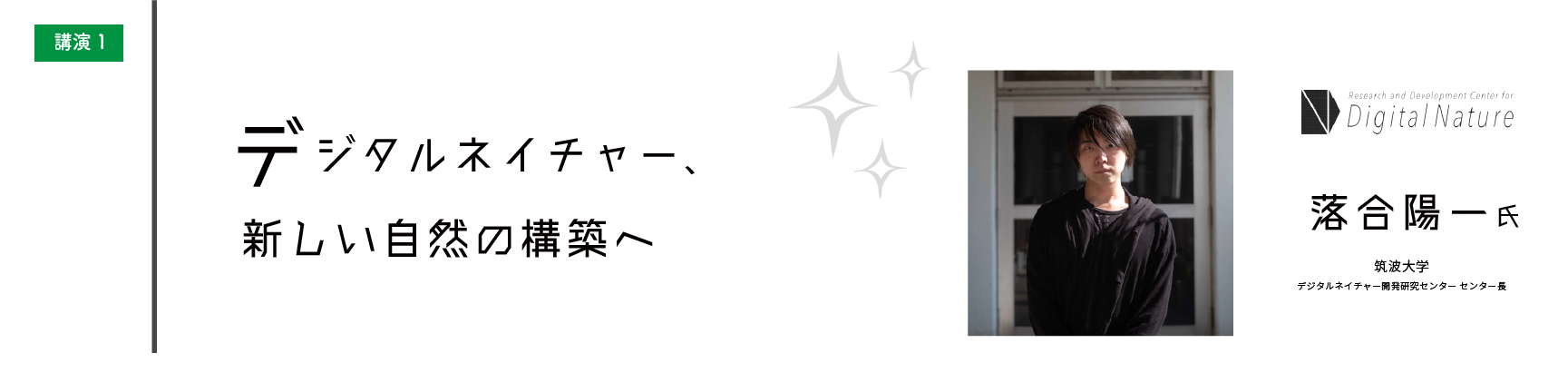
筑波大学でデジタルネイチャー開発研究センターのセンター長を務めております、落合陽一です。ほかに科学技術振興機構(JST)の研究プログラム「CREST」の研究代表者や、人工知能開発研究センターの職員、ムーンショット型研究開発制度のアンバサダーを務め、大学で教えたりもしています。起業家としてはピクシーダストテクノロジーズ株式会社の代表取締役でもあります。ニュース番組の「news zero」や、ソーシャルメディアNewsPicksの番組「WEEKLY OCHIAI」に出演しているのをご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。メディアアーティストとして、2010年頃から作家活動もしています。
今日は私が興味を持っていることをお話しするために、私がメディアアートの父だと思っている、Nam June Paik(ナム・ジュン・パイク=白南準)の話から始めようと思います。彼が1980年に雑誌に寄稿したエッセイの中で述べた、「ステーショナリー・ノマド(stationary nomad)=定在する遊牧民」という概念についてです。彼は「音楽やダンスが絵画より古くから栄えたのは、重量を持たず脳に記憶される芸術だからだ。つまり石油危機は重力の問題だ」と指摘しました。そして「人類は何百万年もの間、60kgの体を動かすのに60kgの体しか動かさなかったが、この50年間は、60kgの体を動かすために300kgの車を動かしてきた。これはこれまでに発明された中で最も愚かなシステムだ。この状況を打破し、石油の使用を廃止する唯一の方法は、体を動かさずにアイデアを動かすことだ」と述べ、これを「ステーショナリー・ノマド」と名づけたのです。
現代の我々は、今回のように体を動かさずに講演会だけを催す、つまり体を動かさずにアイデアだけを動かすことが実際に可能です。その中で、では何が体を動かすに値することなのか、あるいはどこにこのような考え方のルーツがあるのか。そういったことを考えながら実際の工学研究をしています。
Nam June Paikのエッセイには、他にも興味深い記述があります。それはおおよそ次のような内容です。「次の世紀の絵画は、プログラム可能な電子壁紙になり、遠隔地に絵画を展示するにはプログラムカードを郵送すればよくなるだろう。また電子スチル写真も普及するし、レコーダーとカメラが一体となったポケットサイズの小型カメラが登場し、ステーショナリー・ノマドの後押しになるだろう」。実はこれは、ポケットの中にスマートフォンが入っていて、世界中に電子スクリーンがあり、それを使ってコミュニケーションを取るという、我々にとってはすでに当たり前になっていることです。
つまりどういうことかと言うと、その原因が新型コロナによるとは当時のNam June Paikも思っていなかったでしょうが、結果として出現した世界は、彼が想像していたものに近いということです。このように、芸術と科学技術が合わさったところ、メディアアーティストが新しいものの在り方を考えているところに、何かを変えるためのフロンティアや試金石が転がっていることは多いのではないかということです。
この話が、私の所属するデジタルネイチャー開発研究センターで、大嶋泰介さん・秋吉浩気さんと一緒に行っているセッションにも繋がってきます。一定の材料に人工的な形状を付与するなど、計算機のシミュレーションで生み出せる新しい材料があります。その物性を、例えばヤング率と密度を軸に取ったグラフにプロットしてみると、古典的マテリアルを突き詰めていった素材ではカバーできない領域が埋められることがわかります。このような領域のことを一体何と呼ぶか。メタマテリアル領域と呼んでもいいけれども、それは一方で、計算されたことによる自然領域なのかもしれません。ワクチンでは……と広げて考えていったときに、計算することで生まれる新しい「自然が拡張された自然」の領域がある。それを私たちはデジタルネイチャーと呼んでいるのです。
こうした「自然が拡張された自然」が恐らく存在することは、ここ15年ほどの研究開発の中で十分にわかってきました。今は、それをいかにデジタルファブリケーションに生かすか、サステナビィリティに寄与していくかといった、自然のエコシステムとコンピュータサイエンスが出会うところに埋まっている何か面白いものを探求する方向に動いています。その中でも特に重視しているのが、地産地消のテクノロジーです。いかにサプライチェーンを短く、且つ移動や物流のコストを最小化し、またリユースしながら、そこに付加価値を計上していくか。その方法論にいかに寄与するかが大切なのではないかと思っています。
私がそのキーの一つと考えているのが民芸です。民芸という言葉は柳宗悦の民芸運動から生み出されたもので、柳の定義する民芸はいくつかの条件を伴っています。例えばその一つが実用性です。鑑賞するために作られたものではなく、何からかの実用性を備えたものであること。それから無名性。特別な作家ではなく、無名の職人によって作られたものであること。また労働性。繰り返しの激しい運動によって得られる熟練した技術を伴うものであること。他にも、複数性、廉価性、地方性、分業性、伝統性、他力性など柳の挙げた条件は様々です。
この定義に照らしたとき、いま我々が持っているテクノロジーを使って地産地消のためのアプリケーションをつくること、いわば「テクノ民芸性」には、一体どういった意味があるのでしょうか。例えば柳は「激しい労働によって得られる熟練した技術」と言っていましたが、その熟練技術が3Dプリンターやレーザーカッター、もしくはそういったデジタルファブリケーションツールでコピー可能になったとき、我々の社会においてどういう意味を持つのでしょうか。
その一例となりそうなのが、私がCRESTの研究で取り組んでいるxDiversity(クロス・ダイバーシティ)です。この研究開発プロジェクトでは、障害を持っている当事者や周囲の人の問題発見の方法をまずワークショップによって検討し、その後、具体的なハードウエアやマシンラーニングのチームを作り、データセットをして、公開して、ケーススタディとしてまとめるといった取り組みをしています。
ユーザーが持っているアプリケーションやタスク、つまり個々の置かれた状況は非常に多様です。また眼鏡があれば見えたり車椅子があれば移動できたりと、デバイスで解消できる。「障害は社会によって生まれ、技術によって解消される」というのが僕の持論です。そうした、ユーザーによって異なる環境や条件などの違いと機械学習をクロスさせながら、多くの人に寄り添う問題解決の仕組みをつくること。そして、個別課題から現場共通の課題を引き出し、高性能・高価格なものより、今ある技術を最適化して速攻で使えるようにしていくこと。柳の「民芸の定義」に照らしたとき、これは非常に民芸的な取り組みだと私は考えています。
また我々は、研究プロジェクトとして物をつくるだけではなく、当事者が周囲に支えられながら何かを作っていく作業それ自体を、新しいものづくりとして示すことも大事にしたい。そして、社会によって生まれた障害が技術によって解決されていく瞬間というのを見たいと考えています。
こうしたテクノ民芸的な動きは、これから限界費用が下がり、またIoTデバイスが普及することなどによって拡張していくでしょう。その中で我々は、いかにライフスタイルに資するような研究につなげていくかを、真剣に考えていかなければならないフェーズに入ったのだと思います。つまり、計算機と調和する心豊かな毎日を実現するための、持続可能な新しい自然構築に資する研究とは何だろうかと。
しかし、日々の多様な活動の積み重ね・繰り返しこそが「心豊かな毎日」であるにも関わらず、従来の人間とシステムを繋ぐ工学では、特定のユーザー・場所・場面で発揮される限定的な効果しか研究できませんでした。また、ポストコロナの社会で従来の文化行動様式そのものがリセットされ、供食であったり体験の共有であったりという、イヴァン・イリイチの言う「コンヴィヴィアリティ(自立共生)」を育むような「祝祭」的なものが消失していこうとする中、我々のライフスタイルをどう再定義していくかが重要な課題になりつつあります。そこで私が重要と考えるのは「ステーショナリー・ノマド」化する我々の世界において、限界費用をゼロ化することで生まれる情報の側のフットワークの軽さと、そこにどのようにサスティナビリティを絡ませながらライフスタイルを構築していくかです。
その中では、従来通りの古典的なコワークだけではなく、当事者が発見し当事者が何かを作っていくようなケースも増えていくのではないでしょうか。そうしたより民芸的なものづくりを展開するうえでは、情報科学を使ったコミュニケーションやコミュニティづくりが肝になるはずです。それに対する個別最適化のシステムを、限界費用と限界効用のバランスを考えながらいかに構築するかというのは、地産地消に帰するデザイン設計の一つの形ではないかと思います。
パーソナル化やパラメーター化、多様性、人機融合、実世界志向といった21世紀の価値観は実のところ、計算機によりソフト化・ブラックボックス化されています。その中で、いかに祝祭的な体験、コンヴィヴィアルな、互いに対話しやすく共生しやすい状態を作っていけるのか。例えばいま私が注目している理論の一つに、人間を含む多くの動物は、労せず食を得るよりも何か対価を払うほうを好む「コントラフリーローディング(逆たかり行動)」という性質を持つ、というものがあります。何かしてもらったら何か返さないと悪い気がするとか、持ちつ持たれつとかいう感覚です。そういった我々の個別の性質をも視野に入れつつ、問題提起のためのプロトタイプを作ってマーケットに問う、そのサイクルを回し続けることが、私のようにユーザーに近い研究をしている研究者のすべきことではないかと思っています。
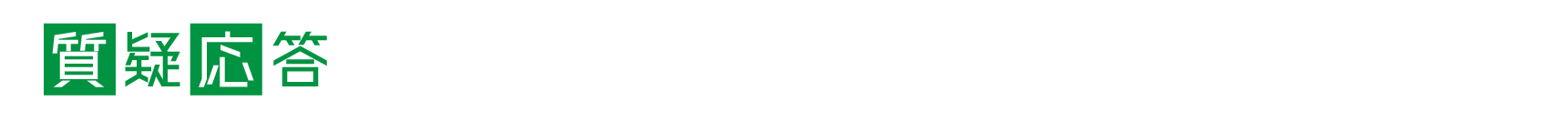

新しい科学やイノベーションを社会に浸透させるには、周囲を巻き込んでいく力が重要だと思いますが、落合先生がそれを実現するために心掛けていることは何ですか。

私は研究者ですがアーティストでもあり、技術を批判的に見ている側面が強いと思います。技術への信頼や期待と、技術への懐疑、その両方の価値観を行き来しながらちょうどいいあたりを見据えていくことが、特に人間に関わる工学研究の領域では重要だと考えています。さめた目で見ることと、やっていることの楽しさを忘れないことを心掛けています。作って、対話し、対応する、ファブ・アンド・コミュニケーションとも言えるかもしれません。

解決したい問題や使ってみたいテクノロジーの発見は、ワークショップが起点になるのでしょうか。それとも、最初からこういうものを作りたいというイメージがあるのでしょうか。

空想上の誰かのために作ったシステムは、ほぼ役に立ちません。製品化できそうというより、身近な人の課題に対応するのに必要そうだということが先にあり、そのうえで、課題を自分ごととして開発に臨むためにワークショップがあり、互いが仲良くなるうちに、その技術が役立つ対象者が増えるという流れだと思います。

課題解決の手法についてのお話がありましたが、落合先生にとってアートはどのような位置付けでしょうか、課題解決の手法なのでしょうか。

アートとは、新しい挑戦が何らかの形で人類の文化的教養や価値につながっていき、より豊かな人生を育むものだと思っています。それをヨーゼフ・ボイスの言う「社会彫刻」のように、広く人類が総合的に造形しうる形と考えれば、それは優れた科学から作られるものとも近いのではないでしょうか。工学からは、もちろん実用的なものも多く生まれます。ただ私から見れば、例えば車輪の形は、工学が見出した新しい着地点であると同時に、単純な美しさや文化的成熟を感じさせるものでもあるのです。そうした、サイエンスとアートの双方の根幹に極めて近いところに存在するかもしれない普遍性を期待して、アートと向き合っているように思います。

自閉症等、精神障害に端を発するコミュニケーション障害がテックで解決できる可能性について、落合先生のお考えをお聞かせください。

私は医師ではないので素人なりに考えることですが、特に精神医療に関しては、20世紀流の単純な「分類」では扱えなくなりつつあるのが現状のように見えます。そうした時に、当事者一人ひとりを個別具体的に見るアプローチに関しては、コンピュータは間違いなく重要な位置を占めると思います。一人ひとりを観察することや、その人に合ったコミュニケーションを考えること、問題が発生しそうなリスクファクターをある程度緩和するようなことはできるかもしれません。
